 価値あるイノベーションを生み出すためには、科学的“独創”と社会的“共創”が大切だ
価値あるイノベーションを生み出すためには、科学的“独創”と社会的“共創”が大切だ
国立研究開発法人 科学技術振興機構
研究開発戦略センター センター長
博士(工学)
野依 良治
「化学のすごい力」に心を躍らせた少年時代。行く道を自ら定める
湯川秀樹博士が日本人として初めてノーベル賞を受賞し、日本中が沸き返った1949年、小学5年生だった野依少年もまた、その偉業に心をときめかせた。その後化学に目覚めたのは、化学技術者だった父親の影響が大きい。

本取材は、2017年12月13日、東京都千代田区五番町の
科学技術振興機構「東京本部別館」で行われた。
野依氏は現在、同機構の
研究開発戦略センター長を務めている
僕が小学校に上がったのは終戦の年。田舎に疎開していたので難は逃れましたが、家があった神戸は爆撃を受けて焼け野原状態でしたし、食べるものにも着るものにも不自由する悲惨な環境にありました。そんな時代ですからね、国民は皆、湯川先生の快挙に励まされたものです。実は、僕の両親は若き日の湯川先生と偶然、海外旅行をともにしているんですよ。化学会社に勤めていた父が研修でヨーロッパ視察へ向かった際、長い船旅をご一緒しました。なので、ノーベル賞受賞を知った時は、「あの先生!」と我が家は大騒ぎ。面識のない僕も子供心に誇らしく、そして湯川先生がいらした京都大学にも思いを寄せるようになったのです。
化学に目覚めたのは、灘中学校の入学式を目前に控えた頃。父に連れられて行ったナイロンの製品発表会で、化学の力に驚かされたのがきっかけです。東洋レーヨン(現東レ)の社長が「ナイロンは石炭と水と空気からできている」と話すのを聞いて、「化学こそがタダ同然のものからすごい価値を生む」と、えらく感動したのです。加えて、父の口癖にも感化されました。当時、化学産業においては技術輸入が主流だったなか、父は常々「こんなことではダメだ。国産の産業技術なくして日本の経済復興はない」と繰り返す。こうした環境があって、「将来は化学技術者になって社会の役に立つ」という意識が培われていきました。
野山を駆け巡り、草野球に夢中になりと、子供の頃からやんちゃだった。関西の名門校である灘中学・灘高校に進学してからも文武両道で、6年間、柔道に打ち込んだ。「勉強もそこそこできたけれど、それより腕力と気力に自信があった」と振り返る。立派な先生陣と〝よき悪友たち〞に恵まれ、野依は存分に学校生活を謳歌した。
その後、幼き日の思いのままに京都大学に進学しましたが、初めて親元を離れたこともあり、それは熱心に遊んだものです。大学より京都の街から多くのことを教わったといっても過言じゃない(笑)。何も学問が不得手、きらいだったわけじゃなく、教養課程の講義よりも新鮮で刺激的なものに魅せられていたという話です。
とはいえ、最終学年の卒業研究のためには、所属する研究室を決めなければいけません。僕が門を叩いたのは、有機天然物化学担当の宍戸圭一教授で、まさに恩師との出会いとなりました。先生の導きで、ここからは勉学一途。この頃、優秀な工学部学生の多くは、学部を卒業してストレートに産業界に入る傾向があり、大学院進学は主流ではありませんでした。でも、それまでの勉強不足を自認していた僕は「頭脳を鍛え直すために〝入院〞する」と言って、大学院に進むことにしました。その際、直接指導してくださったのが、京大きっての俊英と称された野崎一助教授で、先生もまた僕の恩師です。
60年代前半の頃ですから、日本には先端機器などほとんどなく、研究環境は非常に貧しいものだった。それでも僕は化学に魅了され、猛烈に勉強し始めました。野崎先生からは「新しい有機化学を拓け」と鼓舞され、頬がこけるほど実験などに夢中になったものです。今の若い研究者が行っているような高度な研究ではなく、いわばアマチュア精神での研究でしたが、「生涯没頭できるものに出合った」という感覚を得たのはこの時代でした。
※本文中敬称略
名古屋大学への転任と米国留学。新しい環境で志を高めていく
「いずれは産業界で活躍したい」という思いを胸に修士から博士課程へ進もうとしていた矢先のこと、野依の人生設計が大きく変わる出来事が起きた。教授への昇進を控えた野崎氏から「助手になってほしい」と声をかけられたのである。分不相応な任だと辞退したものの、結局は押し切られ、野依は産業界に身を投じる機会を失した。しかし大学に残り、自由な研究に臨んだことで、後のノーベル賞受賞の芽となる「不斉合成」の原理を発見したのである。

1961年、京都大学工学部を卒業。
恩師の宍戸圭一教授(前列中央)、野崎一助教授
(前列左)らとともに。後列左から3人目が野依氏
まだ博士の学位も取っていない27歳の助手でした。カルベンの反応性について研究していたなか、銅原子とある種の有機化合物を組み合わせた触媒を使うと、右手形と左手形の物質が偏ってできることを偶然発見したのです。
有機化合物には原子の構成が同じでも、人間の右手・左手の関係と同様、鏡に映した時のような形の違いがあって、これらはキラルな化合物と呼ばれ、生体への働きが大きく違うことが多い。生物は酵素を使って片方だけをつくる能力を備えているわけですが、普通の人工合成では左右の形が同じ数できてしまう。かつて、天才科学者パスツールは「化学や物理の力では左右の識別は不可能である」と言っており、有用な生物活性を持つものだけを人工合成する手法は、100年以上にわたって科学者の夢だったのです。後に一大分野に発展する「キラル有機金属分子触媒による不斉合成」の原理発見は、まさに、新たな化学の発展の端緒をつかんだものでした。
ただ、この不斉カルベン反応による生成物は、当時としては一般的でない三角形状化合物で、左右選択性も55対45と実用性に乏しかったから、国際学界のみならず、産業界からもまったく評価されませんでした。祝福してくれたのは京阪地区の研究仲間だけ。僕はよく言うんですけど、事実の発見より価値の発見が大切だと。新事実を主張しても何もならないわけで、重要なのは「それが何を意味するか」です。僕らが観察した化学的事実はささやかなものだったけれど、でも、パスツールへの挑戦の道筋となる原理的〝価値〞は極めて大きいと思っています。
世界は認めなかったが、この成果を伝え聞いた名古屋大学理学部から招聘がかかった。それまで縁もゆかりもなかったから「驚いた」そうだが、野崎氏の後押しもあり、68年、野依は母校を後にして名大助教授に着任。独立した研究室を任されることになった。不斉カルベン反応への思いは一旦断ち、新たな環境に踏み出したのである。
まだ29歳の僕の登用は、平田義正先生による人事だったようです。フグ毒の構造の解明で有名な天然物有機化学の巨人ですが、着任してすぐ、こんな要請がありました。「私は天然物有機化学をやるから、それ以外は野依さんにお願いします。そして名古屋の有機化学をよくしてください」。この言葉は大変に重かった。何でも自由にやっていいという話ですが、これこそ難題というもの。有機化学の分野は広いですから。好奇心に導かれて本当にいろいろなことをやりましたね。一点集中型ではなく分散型で、〝やり散らかした〞感じはあるのですが、大先生の要請に応える決意は固いものでした。
大学紛争のさなかにあった69年、僕は以前から予定していたハーバード大学のE・J・コーリー教授のもとに留学しました。教授の厳しさは有名で大変だったけれど、ハーバード大学の有機化学の黄金時代に居合わせることができたこの機会は、本当に多くの学びをもたらしてくれた。実は、コーリー教授の化学合成の研究に携わりつつ、密かに有機金属化学の勉強もしていたのですが、それは自分の「今後の生きる道」を模索していたから。そのなかで僕は、やはり最も基本的な水素化反応をやろう、それも左右を区別して水素化する「不斉水素化反応」に挑戦すべきだと決意したわけです。
これには、イギリスから来ていた助教授で、分子触媒の立役者であるジョン・A・オズボーン博士の存在が大きくかかわっています。同年輩で気が合ったし、彼が開発した均一性水素化触媒に興味があったから、よく教授室を訪ねては四方山話をしたものです。新しく生まれつつあったサイエンスに触れ、かつそれを生み出した人に直接会えたことは大きかった。後に、ノーベル賞を共同受賞することになるK・バリー・シャープレス博士と出会ったのもここですし、ほかにも多くの知己を得ました。一緒に成長していったという思いが強いし、若い時に育んだ友情は、一生の宝物だと思っています。
※本文中敬称略
信念がもたらしたノーベル化学賞。産業界にも大きく貢献
名大に戻り、野依が「不斉水素化反応」の研究を本格的に始めたのは74年。京大での不斉カルベン反応の発見と、ハーバード大での水素化反応の経験が、ようやく交差したのだ。実践的不斉合成反応の可能性を捉えた60年代は、学界も産業界もまともに相手にしなかったが、この頃にはすでに、有機化学界の中心的な課題になっていたという。
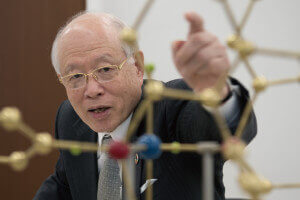
盟友であった高谷秀正君とともに始めました。不斉水素化反応を実現するためには、触媒作用を持つ金属と、分子の左右の違いを厳密に識別するキラルな鋳型分子を結合させた触媒をつくる必要がある。僕らが鋳型分子として選んだのは、BINAPという分子。これにロジウムを結合させた分子をつくって、不斉水素化をやろうと考えました。このBINAPは実に美しい形をしていて、世界中の化学者が憧れた〝美女〞なんですよ。ところが美女は人を惑わす。まったくうまくいかなくて、計画した水素化触媒が誕生するまでに6年もの歳月を費やしました。同様にBINAP合成を競っていた研究者たちは早々に断念していたから、美女を獲得した時は誇らしかったですね。
それでも研究は困難を極めました。〝彼女〞は直ちに「不斉異性化」によるメントール工業生産を可能にしましたが、「不斉水素化」には制限が多い。結局、所期の目標に到達したのは、さらに6年後のことです。成功のカギは、BINAPの相棒をロジウムからルテニウムに置き換えたこと。あとは一気呵成でした。この触媒上では様々な有機化合物の水素化が何万回も何百万回も繰り返し起こり、右手形、左手形だけを選択しながら目的の物質が大量にできる。これで長年の懸案であった化学上の一つの問題を本当に解決し、有機合成化学の方向を大転換させることになったのです。
信念の下、厳密に計画を立てて、注意深く実験を重ねても予想どおりの結果を得られないことは多々ある。でも、それを失敗と呼ぶのは適切ではなく、うまくいかないのには必ず科学的な意味があります。単に失敗と打ち捨てず、しっかり事実を整理して把握し、深く考え直すことが重要です。予期に反する結果こそが神様の思し召し。困難の克服は、成功するための不可欠な条件だと思いますね。
ノーベル化学賞の共同受賞の報を受けたのは01年10月のこと。賞設立100周年というタイミングだった。受賞理由は、次のように記述されている。「化学のみならず材料化学、生物学、医学の研究の急速な進歩に貢献するものであり、アルフレッド・ノーベルの精神にもまさに合致する。3名の業績の人類への有意義な貢献はすでに多大なものがあるが、分野後継者の研究によってさらに増幅されるであろう」。
将来の可能性も含めて、大変仰々しく褒めていただいたわけです。30年以上にわたって自由に研究をさせてくれた名大、そして協力してくれた学生たち、長く一緒に研究してくれた仲間の献身に、ようやく報いることができたという思いが強かったですね。無条件で一番喜んだのは、やはり当時87歳の母だったと思います。終戦後の貧しい時代に、苦労してやんちゃ坊主を育ててくれた母にも親孝行はできたかなと。「貢献はすでに多大なものがある」。この評価を得た背景には、高砂香料工業を中心とする世界に先駆けた勇気ある事業展開があります。例えば、同社や大阪大学などと共同で臨んだメントール合成はその代表例。量産体制を確立したのは83年ですが、日本の化学界が誇る世界最大規模の不斉合成プロセスは、今も世界の需要を支えています。不斉水素化は医薬品でいえば、抗菌剤や抗生物質などの製造技術として実用化されています。もちろん、これらは企業の功績ですけど、幼い日に産業界を目指した僕もわずかながら貢献することができた。科学の可能性に懸ける同志ともいうべき産業人に出会えたのは幸せでした。僕らの化学の力量を証明してくれたのですから。
とはいえ、これらはもう昔の話で、その後のサイエンスの驚異的な発展を考えれば、たいしたことじゃありません。今の若い人たちはもっと高水準の研究をやっているわけで、つまり、科学は数多の発見や技術を集積することで日々進歩し続けているのです。新しいことを一つ見つければ、未知のことがまた出てくる。「無知の知」というソクラテスの言葉がありますが、無意味な競合や利得、虚栄にとらわれるのではなく、我々は科学というものの本質に対して常に謙虚でなければいけない、本当にそう思っているんです。
※本文中敬称略
科学技術のナビゲーターとして、後継世代の育成に尽力
現役の大学教授時代から文部科学省の学術や科学技術施策にかかわり、野依は長く社会的活動にも尽力してきた。03年には、請われて「新生・理化学研究所」の理事長に就任、10年以上にわたってその大きな運営責任を担ってきた。JSTの研究開発戦略センターの長にある現在は、「科学技術のナビゲーターとして、後継世代を励まし育てていくことが役割」だと語る。

あらためて考えれば、科学者や技術者は社会で少数派ですから、まずは科学技術の大切さを社会全体に周知してもらって、政府や産業界もひっくるめた〝社会総がかり〞で振興をしなければなりません。科学者や技術者個人に丸投げされても無理ですから。そのためのナビゲーターとして精一杯働くというのが、目下の最大の任務です。
現代の大学研究に対する提言はいろいろとありますが、大きく気になっているのは基礎研究と応用研究の二元論。これは無意味です。科学知識とその実用があって初めて社会的な果実になるわけで、俯瞰的に見れば一体ですよね。1人の科学者による独創的な発見をもとに、10人、100人が協力して優れた技術を発明し、さらに1000人が知恵を集めて新しい社会価値をつくる。これが、昨今でいうイノベーション。社会を変えるような価値を生み出すには虫の目、鳥の目、魚の目を合わせた包括的な考え方が不可欠で、それを実践できるプラットフォームをつくることが喫緊の課題。基礎研究と応用研究で足の引っ張り合いをしているようでは、国は滅びます。
かつて大学では、個人の〝独創〞が尊重されてきました。相対性理論やDNA二重らせん発見のような、波及効果が計り知れない独創例はアカデミアにおける基本であり、若者にはぜひ未踏に挑んでほしい。しかし一般論でいえば、個人が独創性を発揮できる分野、事柄には限界があります。イノベーションを生み出すためには、他の知識や知恵との〝共創〞がとても大切になる。ところが日本の教育はこの認識が極めて不十分で、入学試験にしても自己中心傾向を助長するし、学問はどんどん細分化されてむしろ共創文化を阻んできた。オープンサイエンス、イノベーションの時代においては、密接な産官学協力や頭脳循環は必然なんですよ。
科学者として成功する道――野依によれば、それは単純だという。「自らいい問題を見つけて、それに正しい答えを出すこと」。そして、それを実現するために「もっと翼を広げてほしい」と、野依は後継世代の研究者たちにエールを送る。
単純だけれど、いい問題を見つけることは、答えを出すよりも難しい。僕はセレンディピティが重要だと思っていて、科学の創造というのは、過去の知識に基づく合理的な思考だけでは遠く及ばない。特に大きな発見は、偶然の幸運を呼び込む力、セレンディピティによってもたらされると信じています。
創造的な研究につながるいい問題を見つけるには、井の中の蛙ではダメで、国内だけでなく海外に飛び出して様々な〝異〞と出合って触発されるのが一番有効だろうと思うのです。ノーベル賞を受けた人たちの受賞時点までの動きを見ると、平均4・6カ所の研究機関を経験しているんですね。いろいろと動くことによって視野が広がり、触発されていることは確かです。これからの共創時代は、世界を渡り歩いて自らを磨き、そして人脈をつくって共同研究することがカギになります。
だからこそ、若い学生や研究者たちには「もっと翼を広げろ」と言いたい。博士号を取得した後、もっと様々な分野で活躍してほしいのです。サイエンスは社会のあらゆる分野とかかわっているのだから、大学だけが自分を生かす場ではありません。産業界、政府機関、NPOやNGO、あるいはベンチャー企業など、そういった場で活躍することを真剣に考えるべきだと思う。そして、日本社会は夢を持つ若者を励ましながら育成し、旧弊的な考えや体制の新陳代謝を徹底して図っていかなければなりません。そこに尽力することが、今の僕の役割。何といっても、未来社会を支える科学技術を担うのは若者なのですから、ここで立ち止まっているわけにはいきません。
※本文中敬称略
Profile
 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター センター長 博士(工学)
国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター センター長 博士(工学)
野依 良治
| 1938年9月3日 | 兵庫県武庫郡精道村(現芦屋市)生まれ |
|---|---|
| 1961年3月 | 京都大学工学部 工業化学科卒業 |
| 1963年3月 | 京都大学大学院 工学研究科修士課程修了 |
| 4月 | 京都大学工学部助手 |
| 1968年2月 | 名古屋大学理学部助教授 |
| 1969年1月 | ハーバード大学博士研究員 |
| 1972年8月 | 名古屋大学理学部教授 |
| 1996年4月 | 名古屋大学大学院 理学研究科教授 |
| 1997年1月 | 名古屋大学大学院 理学研究科長 |
| 2002年3月 | 日本化学会会長 |
| 2003年10月 | 独立行政法人 理化学研究所理事長 |
| 2005年2月 | 文部科学省 科学技術・学術審議会会長 |
| 2006年10月 | 教育再生会議座長 |
| 2015年6月 | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター長 |
| 2015年7月 | 科学技術館館長 |
主な受賞
日本化学会賞(1985年)、朝日賞(1993年)、
テトラヘドロン賞(1993年)、日本学士院賞(1995年)、
アーサー・C・コープ賞(1997年)、ウルフ賞(2001年)、
ロジャー・アダムス賞(2001年)、
ノーベル化学賞(2001年)ほか多数
主な栄典
文化功労者顕彰(1998年)、文化勲章(2000年)、
ローマ法王庁科学アカデミー会員(2002年)、
日本学士院会員(2002年)、
全米科学アカデミー外国人会員(2003年)、
英国王立協会外国人会員(2005年)、
中国科学院外国籍院士(2011年)ほか多数
コメント