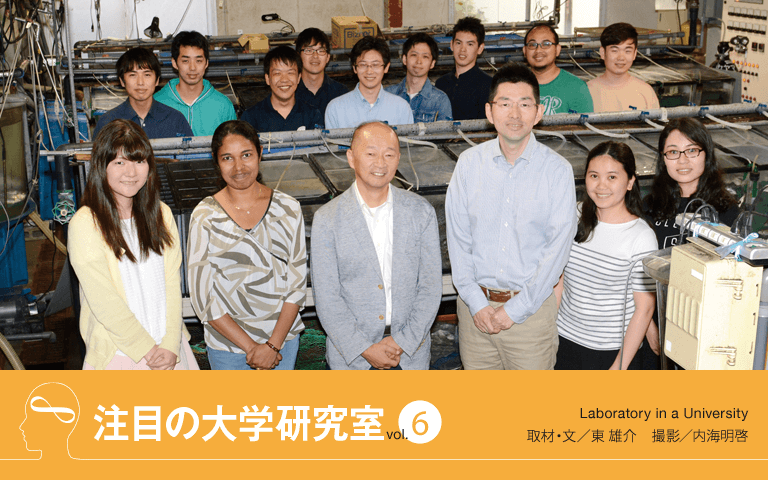
東京海洋大学 海洋生物資源学部門 水族栄養学研究室
教授 博士(農学) 佐藤秀一
魚で魚を育てる養殖業から脱却
養殖魚を育てる飼料は、生魚の切り身や小魚を乾燥させた魚粉が主である。いずれにしても「魚で魚を育てる」のが今の養殖業だ。だが、天然魚の食料を奪うことになるため、生態系を壊す危険があると指摘されてきた。加えてここ数年、魚粉の価格が3、4倍に急騰し、養殖業者を悩ませている。国内の養殖漁業の生産量は横ばいだが、世界的には増加傾向。にもかかわらず、魚粉の原料となる南米におけるカタクチイワシなどの生産量の制限などにより、需給バランスが崩れたのだ。
現在、求められているのは魚粉に代わる新たな飼料。佐藤秀一教授は「植物性飼料で魚を育てる」研究に取り組んでいる。
成功すれば、ベジタリアン養殖魚が誕生するわけだ。主な原料は大豆やトウモロコシ。大豆油やコーンオイルの絞りカスを使用するため、価格と共に環境負荷を抑えることができる。
「つまり魚にも人間にも環境にも優しい餌なのです」と佐藤教授。すでにニジマスやコイ、マダイ、ブリについては植物性の飼料での育成に成功している。
ここに至るまで、クリアするべき課題が2つ存在した。第一に「養殖魚が食べてくれる餌にすること」。これまで魚由来の飼料を食べてきた養殖魚たちは植物性飼料に慣れておらず、一口で吐き出してしまう。食べさせるには、これは美味しい餌であると”騙す”必要がある。
「現在は”ふりかけ”みたいに、植物性飼料原料に魚のエキスを噴霧して食べさせています。鰹節をつくるときに出る煮汁を濃縮したようなものですね」
第二の課題は、魚種により異なる栄養要求に応えること。例えばニジマスやコイなどの淡水魚は自らタウリンをつくり出せるが海水魚は不可能。DHAも同様だ。淡水魚はリノレン酸という脂肪酸からDHAを生成できるが海水魚はDHAを含む餌を食べることで体内にDHAをため込む。海水魚に食べさせる飼料にはこれらの栄養素を添加する必要があることがわかった。
「魚が食べさえしてくれれば、100%植物性の飼料でも十分育つことは実証済みです」
今後は養殖業者への導入を促すフェーズに進む。魚粉の含有量を30~50%まで減らし、部分的に植物性飼料で代替する養殖業者は現れている。しかし長年使い続けてきた魚粉飼料から植物性飼料へと180度切り替えるにあたり、養殖業者に不安があるのは否めない。
「皆さんに安心して使っていただけるよう、現在は水産庁と連携しながら、実際の養殖業者さんに植物性飼料を使っていただく実証実験を行っています」
ベジタリアンマグロ。産学連携で実現へ
「植物性飼料で魚を育てる」研究のゴールはベジタリアンマグロの実現だ。クロマグロが絶滅の危機に瀕しているのは周知のとおり。しかも自分の体重の14倍もの天然魚を食べるといわれるクロマグロである。100%植物性の飼料により養殖できれば、水産資源の保護に大きく寄与する。しかし、立ちはだかる壁は高い。極めてデリケートな性質を持つクロマグロは他の魚種に比べて植物性飼料を騙して食べさせるのが格段に難しい。
そもそも東京のキャンパス内で巨大なクロマグロを飼うこと自体がほぼ不可能なのだ。
「なので、マグロの養殖をしているマルハニチロとタイアップして研究を進める計画です。いつまでに、とはお約束できませんが、僕が定年退職するまでには実現させたい(笑)」
もともと水産には興味がなく、熱帯魚や金魚を飼うのが好きだったという佐藤教授。「楽しみながら気楽に」学んでいるうちに現在の専門である魚類栄養学にたどり着いた。その経験から若い研究者に「いきなり最先端の研究を狙わなくてもいい」とアドバイスする。
「最初は偉い先生に重箱の隅をつつくような研究をやらされるかもしれない。でもそこで地味に地道に頑張れば大きなテーマにつながることがありますから。世界の人口がますます増えるなか、それを賄うタンパク源として養殖魚が担う役割は非常に大きい。大げさですが、魚で人類を救いたいと思っています。先輩の先生は『地球を救うのは愛ではなく鯉である』なんて言っていましたけどね(笑)」

この水族栄養学研究室に配属された当初は、魚粉に含まれるリンやマンガン、亜鉛などの無機質を魚がどう利用しているのかといった「重箱の隅をつつくような研究から始めた」佐藤教授。のちに魚粉に多く含まれるリンが栄養素の利用を妨げていると判明。「これを機に、魚粉に代わる原料で飼料をつくれないかと考えるようになりました」
注目の研究
完成している植物性飼料は、大豆やトウモロコシの油かすからとった植物性たんぱく質に、タウリンやDHAなどの栄養素を添加し、ペレット状に成型したもの(左上)。魚種によって栄養素の配合や大きさを変える。実験用にキャンパス内で飼育している魚は、ニジマス、コイ、マダイ、ヒラメ、ティラピアなど。「研究用には、成長が早くない魚がいい」(佐藤教授)。魚体が大きいブリは、長崎県の水産試験場などに飼育してもらい、共同研究している。ほか、飼料メーカーとの連携も進める。ちなみに、植物性飼料100%で養殖された魚は、魚粉により育った魚に比べて魚臭さのない、さっぱりした味わいになるという。「やがては人の好みに合わせて魚の味もコントロールできるようになるでしょう」

佐藤秀一
教授 博士(農学)
さとう・しゅういち/1957年、新潟県生まれ。81年、東京水産大学(現東京海洋大学)水産学部増殖学科卒業。82年、同大大学院水産学研究科修士課程中退。その後、同大助手、講師、助教授、教授を経て、現在は、東京海洋大学海洋科学部学術研究院 海洋生物資源学部門教授。海洋科学部長。
モンサントのGMトウモロコシを食べ続けたラットは巨大腫瘍発生。
トウモロコシ飼料はだいたいがGM作物。
トウモロコシや穀類などで育てた魚は
食べた人間も、遺伝子異常が起きますよね。
食べる野菜のミトコンドリア内膜に異常タンパク質が蓄積すると
雄性不稔になり、
それが男性の不妊症の原因にもなり、悪性ガン多発原因にもなるそうです。